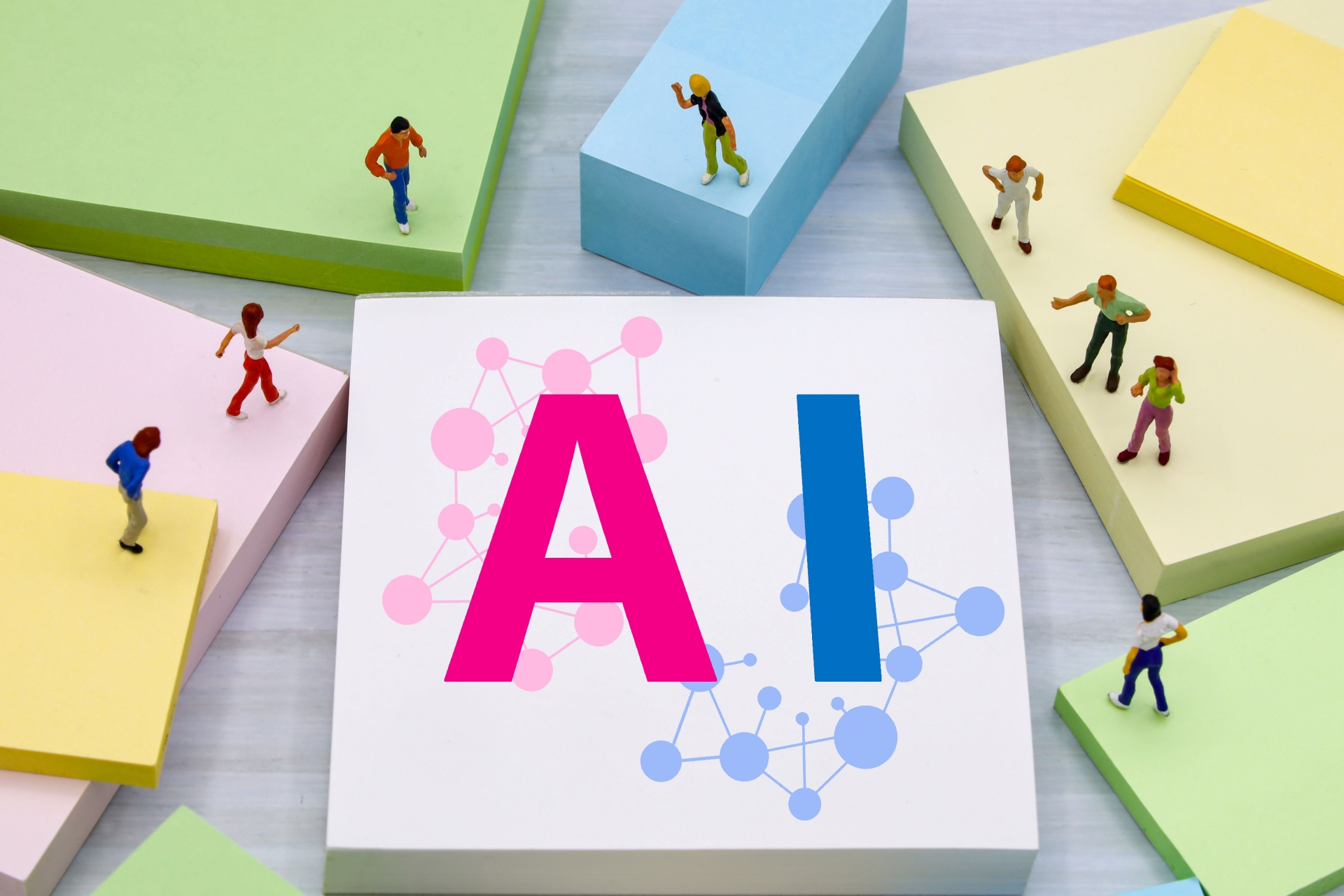AIの活用についてのご案内
当院では、より的確な説明やご提案を行うために、AI(人工知能)を補助的に活用することがあります。たとえば、特定の症状に関する情報提供や、施術以外の医療分野に関する参考意見を検討する際などに用いています。
使用するAIは、個人を特定できないよう匿名化した形で利用しており、最終的な判断およびご提案の責任は、すべて担当施術者(鍼灸師)にあります。AIの利用をご希望されない方は、お気軽にお申し出ください(オプトアウト可能です)。ご不安やご質問がある方は、遠慮なく個別にご相談ください。
【補足】
AIの使用有無は、施術の質に直接影響するものではありません。使用された場合でも、回答文等はすべて施術者が確認・編集し、責任を持ってお伝えしています。
発行日:2025年6月10日
発行者:白石健二郎(鍼灸師)
田無北口鍼灸院
📄 Notice Regarding the Use of AI
At our clinic, we may utilize artificial intelligence (AI) as a supplementary tool to provide more accurate explanations and suggestions.
For example, AI may be used when offering information related to specific symptoms or when considering general opinions in medical fields beyond acupuncture.
The AI is used in an anonymized manner that does not identify individual patients, and all final decisions and recommendations are the sole responsibility of the practitioner (acupuncturist) in charge.
If you do not wish to have your information used in this way, please feel free to inform us. (Opt-out is available.) If you have any questions or concerns, you are also welcome to speak with us directly.
【Additional Notes】
Whether or not AI is used has no direct impact on the quality of treatment.
Even when AI is used, all responses and suggestions are carefully reviewed and edited by the practitioner, who remains fully responsible for their content.
Issued on: June 10, 2025
Issued by: Kenjiro Shiraishi (Licensed Acupuncturist)
Tanashi Kitaguchi Acupuncture and Moxa Salon
具体的に、鍼灸院でAIを使う場面とは?
更新日:2025/06/17 08:36
ご質問を受けた際に口頭ではお伝えしてきましたが2025/06/17 08:20PCからGemini2.5で出力した結果をこちらに貼っておきます。
質問内容:
動悸を訴える患者さんが鍼灸院に来ます。心臓や不正脈など器質性の問題か、自律神経や心因性の問題か?どこで判断すべきでしょうか?もちろん一度病院を受診し医師から器質的な問題がないか、などアドバイスを得たた上で鍼灸院に来るのが理想的ですが必ずしもそうはいかないケースがあります。どのような場合にすぐに医療機関受診を勧めるべきか?教えてください。
応え:
動悸を訴える患者さんが鍼灸院に来院された際、器質的な問題と自律神経・心因性の問題を判断し、適切な対応をとることは非常に重要ですね。特に、すぐに医療機関への受診を勧めるべきケースを把握しておくことは、患者さんの安全を確保する上で不可欠です。
すぐに医療機関受診を勧めるべきケース
以下の症状や状況が見られる場合、器質的な疾患の可能性が高く、速やかに医療機関を受診するよう強く勧めるべきです。
- 胸痛を伴う動悸: 特に、締め付けられるような、あるいは圧迫感のある胸痛が動悸と同時に現れる場合、心筋梗塞や狭心症などの虚血性心疾患の可能性があります。
- 息切れ、呼吸困難を伴う動悸: 少しの動作で息が切れる、あるいは安静にしていても息苦しさを感じる場合、心不全や重度の不整脈、肺疾患などの可能性があります。
- 意識消失、めまい、失神を伴う動悸: 動悸中に意識が遠のく、めまいがする、実際に失神してしまうなどの症状は、致死的な不整脈や重度の心疾患を示唆している可能性があります。
- 冷や汗、吐き気を伴う動悸: 心臓発作のサインであることもあります。
- 安静時にも頻繁に起こる動悸、あるいは持続時間が長い動悸: 一過性のものではなく、頻繁に起こったり、長く続く動悸は注意が必要です。
- 脈拍が極端に速い、あるいは不規則な動悸: ご自身で脈拍を触知してもらい、非常に速い(例:120回/分以上)または明らかに不規則な場合は、不整脈の可能性があります。
- 基礎疾患に心疾患がある、または高齢の患者: 以前に心臓病と診断されている方や、高齢の患者さんの動悸は、より慎重な判断が必要です。
- 突然発症し、かつ今まで経験したことのない強い動悸: 患者さんが「今まで感じたことのない強い動悸だ」「急に始まった」と訴える場合は、緊急性の高い疾患の可能性があります。
鍼灸院での初期対応と判断のポイント
問診や触診、視診を通じて、上記の緊急性の高い症状がないかを確認することが重要です。
- 詳細な問診:
- 動悸の始まり方、頻度、持続時間
- どのような時に起こるか(安静時、運動時、精神的ストレス時など)
- 動悸以外の随伴症状(胸痛、息切れ、めまい、冷や汗、吐き気など)の有無
- 既往歴(心臓病、高血圧、糖尿病など)
- 服用中の薬
- 家族歴(心臓病の有無)
- バイタルサインの確認: 可能であれば、血圧や脈拍(不整の有無も含む)を確認します。
- 体表観察: 顔色、皮膚の色、浮腫の有無なども参考にします。
これらの情報から、上記の「すぐに医療機関受診を勧めるべきケース」に該当すると判断した場合は、速やかに専門医の診察を受けるよう、強く勧め、鍼灸治療は一旦保留とすることが賢明です。患者さんが受診をためらうようであれば、重篤な疾患の可能性や、早期発見・早期治療の重要性を丁寧に説明し、理解を促す必要があります。
一方で、緊急性の高い症状が見られない場合や、患者さんが心因性や自律神経性の関与を強く訴える場合には、心身の状態を詳しく把握した上で、鍼灸治療の適用を検討していくことになります。しかし、その場合でも、「万が一、症状が悪化したり、新たな症状が出た場合はすぐに医療機関を受診してください」という旨を必ず伝えることが大切です。
鍼灸師として患者さんの症状を緩和したいというお気持ちはよくわかりますが、患者さんの生命に関わる可能性のある症状を見逃さないことが何よりも優先されます。医療機関との連携も視野に入れ、常に安全第一で対応していきましょう。
コメント:
開業鍼灸師である限り、このような状況での対応における基本的知識は有していますが、珍しいケースなどは判断に迷うこともあります。その際、このようにAIに質問・相談できると説明や判断のサポートになります。また出力した内容はあくまで参考にとどめ最終的な判断はすべて鍼灸師が責任を負います。
さらに具体的に、鍼灸院でAIを使う場面とは?
更新日:2025/06/19 14:45
患者さんの状況や詳細をより分かりやすく具体的にするため質問の内容を一部変更しました。2025/06/17 14:40PCからGemini2.5で出力した結果をこちらに貼っておきます。
質問内容:
65歳女性 肥満傾向 既往歴はないが母親が狭心症の家族歴あり 主訴は肩こりだが動悸を訴えている患者さんが鍼灸院に来ています。心臓や不正脈など器質性の問題か、自律神経や心因性の問題か?どこで判断すべきでしょうか?もちろん一度病院を受診し医師から器質的な問題がないか、などアドバイスを得たた上で鍼灸院に来るのが理想的ですが必ずしもそうはいかないケースがあります。どのような場合にすぐに医療機関受診を勧めるべきか?教えてください。
応え:
鍼灸院での問診で、患者さんの動悸が器質的な問題によるものか、自律神経や心因性の問題によるものかを判断するのは非常に重要です。特に、65歳女性、肥満傾向、母親が狭心症の家族歴ありという情報から、心臓関連のリスクが高いと考えられます。
医療機関受診を強く勧めるべきケースは以下の通りです。
すぐに医療機関受診を勧めるべきケース
1. 危険な症状を伴う動悸
以下の症状を伴う動悸は、緊急性の高い心臓疾患を示唆している可能性があります。
- 胸痛や胸部の圧迫感: 特に、締め付けられるような痛みや、左腕、顎、背中などに放散する痛みがある場合。
- 息切れ、呼吸困難: 動悸とともに、安静時や軽い労作でも息苦しさを感じる場合。
- めまい、立ちくらみ、失神: 脳への血流が一時的に滞ることで起こる症状で、不整脈などによる重篤な血行動態の異常を示唆する可能性があります。
- 冷や汗、顔面蒼白: ショック状態の兆候である可能性があります。
- 意識の混濁: 重篤な状態を示唆します。
2. 動悸の性質
- 突然発症し、突然停止する動悸: 発作性上室性頻拍などの不整脈の可能性があります。
- 脈拍が極端に速い(120回/分以上)または極端に遅い(50回/分以下)場合: 特に安静時。
- 脈拍が不規則でバラバラに感じる場合: 心房細動などの不整脈の可能性があります。
- 動悸の持続時間が長い場合: 数時間以上続く動悸は注意が必要です。
- 安静にしていても動悸が続く場合: 労作時だけでなく、安静時にも動悸がある場合は、より慎重な判断が必要です。
3. 既往歴と家族歴
- 高血圧、糖尿病、脂質異常症などの基礎疾患がある場合: これらの疾患は心臓病のリスクを高めます。
- 母親が狭心症の家族歴: 遺伝的要因も考慮し、より注意深く観察する必要があります。
- 過去に心電図異常を指摘されたことがある場合: 鍼灸院を受診する前に心臓の検査を受けたことがあれば、その結果を確認することが重要です。
4. 日常生活への影響
- 動悸のために日常生活に支障が出ている場合: 仕事や家事、睡眠などに影響が出ている場合。
- 不安感が非常に強い場合: 心因性の動悸である可能性もありますが、器質的な問題が否定できない中で強い不安を抱えている場合は、医療機関での検査と精神的なサポートの両面からのアプローチが必要になることがあります。
鍼灸師としての対応
上記のような兆候が見られる場合は、ためらわずに直ちに医療機関の受診を強く勧めるべきです。 その際、漠然と「病院に行ってください」と伝えるのではなく、「念のため、心臓の検査を専門の医師にしてもらいましょう」「動悸の詳しい原因を特定するために、循環器内科を受診されることをお勧めします」など、具体的に受診を促す言葉を選ぶと良いでしょう。
また、患者さんが受診をためらうようであれば、具体的な症状(胸痛、息切れなど)が心臓に負担をかけている可能性を説明し、早期発見・早期治療の重要性を伝えることも有効です。
患者さんが医療機関を受診し、器質的な問題がないと診断された上で、自律神経の乱れや心因性の動悸に対する鍼灸治療を検討するのが、患者さんの安全を第一に考えた適切な対応と言えます。
コメント:
具体的なプロンプトにすることで出力もより細かくなりました。そのため患者さんの視点からは専門的で少しわかりにくくなってしまったかもしれません。実際にAIを判断補助で使う場面があれば、その点も考慮し鍼灸師が判断したうえで患者さんにお伝えすることになります。また出力情報はあくまで参考情報で最終的な臨床判断や説明責任はすべて施術者が負います。