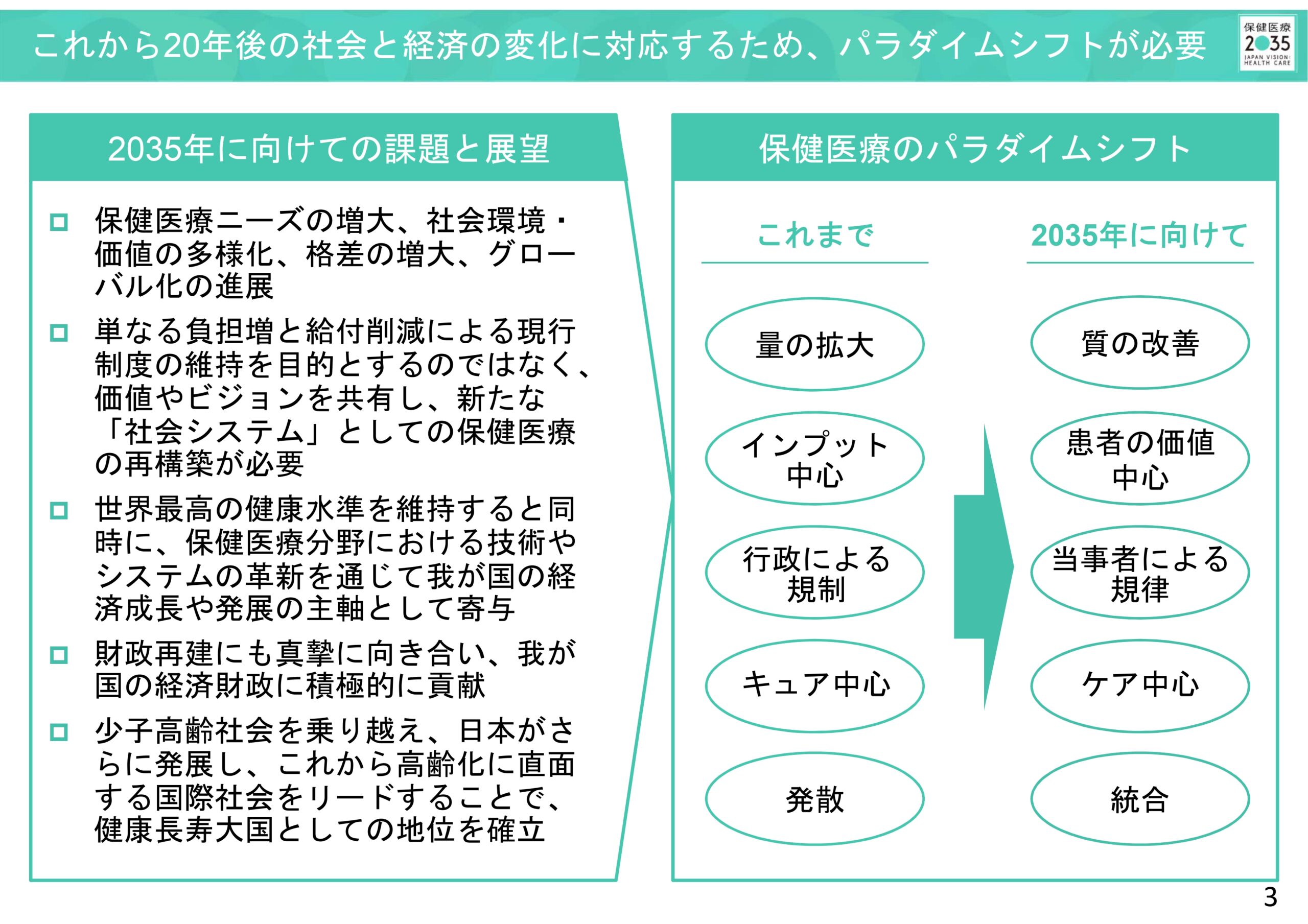立岩真也『不如意の身体』要約と鍼灸治療への生かし方
お世話になっている方から立岩真也さんの「不如意の身体」という本を借りたので、内容の要約や鍼灸治療の生かし方について以下にまとめます。
1. 立岩真也プロフィール
立岩真也(1960年8月16日 – 2023年7月31日)は、日本の社会学者であり、障害学・生命倫理・医療社会学を専門とする研究者だった。特に障害者運動、医療福祉政策、所有論などを中心に研究し、社会の中で障害や病をどのように捉えるかを問い続けた。
新潟県両津市(現・佐渡市)生まれ。東京大学文学部社会学科卒業後、同大学院社会学専攻博士課程に進学。日本学術振興会特別研究員、千葉大学文学部助手、信州大学医療技術短期大学部講師・助教授を経て、立命館大学政策科学部助教授、立命館大学大学院先端総合学術研究科助教授を歴任。2004年より同研究科教授となり、学際的な視点から障害学や医療社会学を探求した。
著書には『私的所有論』(1997年)、『ALS――不動の身体と息する機械』(2004年)、『自由の平等』(2004年)、『希望について』(2006年)、『良い死』(2008年)、『精神病院体制の終わり』(2015年)、『不如意の身体』(2018年)などがある。
2023年7月31日、逝去。
2. 『不如意の身体』の要約(章ごとに詳しく)
第1章 五つある
本書の冒頭で著者は、病や障害をめぐる問題を整理するために、「苦痛(痛み)」「死(死の可能性)」「できないこと(不可能性)」「異なること(差異)」「加害性」という五つの要素を提示します。これらはそれぞれ独立していながら、相互に絡み合って混乱を招くことが多いと指摘しています。
苦痛(痛み):身体的・精神的な苦しみ。本人が感じる苦痛であり、それをどう扱うかが医療や介護の大きな課題になる。
死(死に至る可能性):病や障害がもたらす死の危険。社会が死をどう位置づけるかによって、当事者へのアプローチが変わる。
できないこと(不可能性):障害によって日常生活や社会活動の一部が困難になる。社会モデルとの関連が深い要素。
異なること(差異):健常者と違う特性や外見、能力など。差別や排除につながる一方、「個性」として肯定される場合もある。
加害性:精神障害や行動障害などが社会的に「危険」とみなされる構造。偏見やステレオタイプから排除が生じる。
著者は、五つの要素がどのように組み合わさり、誰にとってどんな意味を持つのかを考えることが、病や障害の理解において重要だと述べます。
第2章 社会モデル
障害を個人の生物学的問題だけではなく、社会の構造によって生み出されるものと捉える「社会モデル」を解説します。著者はこの社会モデルの強みと限界を論じています。
社会モデルの核心:障害の本質は個人の欠陥ではなく、バリアフリーや支援制度など社会環境の未整備にある。
医学モデルとの比較:従来の医学モデルでは障害を治療・リハビリで克服すべきものとみなす。一方で社会モデルは、障害を「社会が取り除くべき障壁」と捉える。
限界:社会モデルを極端に推し進めると、実際の身体的な痛みや生物学的要因を軽視してしまうリスクもある。著者は、両方をバランスよく考慮する必要性を示唆しています。
第3章 なおすこと/できないことの位置
ここでは「治す」という行為に対する見方を問い直します。病気や障害を「なおす」ことは本当に最優先なのか、または社会の側が受け入れるべきなのか、さまざまな角度から検討します。
脳性まひの例:リハビリをすべきなのか、あるいはリハビリに過度に時間を費やすより、社会保障や環境を整えるべきなのか、というジレンマ。
できないことの再評価:環境の改善や技術のサポートによって「できる」ようになるケースもあるが、そもそもできないことを認める姿勢も尊重されるべき。
社会的支援と医療的アプローチの両立:治療だけではなく、周囲の援助や制度整備など、複数のレイヤーから問題を考える必要がある。
第4章 障害(学)は近代を保つ部品である、しかし
近代社会が「能力主義」を基盤とするなかで、障害学が果たしてきた役割を検討します。障害学は、能力主義を批判しつつも、同時に近代の価値観を内在化している面があるという指摘です。
近代と障害学:近代社会は生産性や効率性を重視する。しかし障害学は、それに抵抗しながらも、その枠組みに依拠している部分がある。
能力主義の批判:できないことを理由に人を排除する近代の構造を批判するが、同時に「障害者もできるようにすべき」という発想自体が近代的価値観に縛られている可能性。
新たな視点の必要性:障害学が社会を批判しつつも、近代を乗り越える方向へ進む道を模索していると著者は論じています。
第5章 三つについて・ほんの幾つか
「異なること」「苦しむこと」「死ぬこと」という三つのテーマを取り上げ、それぞれに対する社会の見方や当事者の受け止め方を考察しています。
異なること:他者と違う特性や外見をめぐって、差別や偏見が生まれる一方で、個性として尊重される場合もある。社会が「差異」をどう扱うかによって、障害に対する態度も変わる。
苦しむこと:痛みや苦しみは、本人の生活を圧迫すると同時に、支援やケアを求めるきっかけになる場合もある。苦しみを否定するだけでなく、その存在意義を考える必要がある。
死ぬこと:障害や病が死へとつながる可能性を秘める。死と向き合うことで見えてくる社会の価値観や、その中での当事者の選択肢をどう保障するかが問われる。
第6章 加害のこと少し
精神障害や行動障害を持つ人が「加害者」とみなされやすいこと、あるいはその危険性が過大視されがちなことに注目します。
社会防衛の論理:社会は「危険な存在」を排除することで安全を確保しようとする。しかしそれは当事者の権利を大きく制限する可能性がある。
実際のリスク:加害行為の発生率や要因は多面的に考えられるべきで、障害があるからといって一律に危険視するのは偏見。社会的サポートが脆弱なことがむしろ事件を引き起こす一因ともなる。
第7章 非能力の取り扱い――政治哲学者たち
ロールズやヌスバウムなどの政治哲学者の議論を参照しながら、重度障害をもつ人の「非能力」を社会がどう扱うべきかを考察しています。
ロールズ:社会契約論の枠組みで「正常な協力メンバー」を想定し、重度障害者を理論の外に置いてしまう傾向がある。
ヌスバウム:ケイパビリティ(潜在能力)に着目し、すべての人が一定水準の生活を営むための支援を主張するが、ある水準を設けること自体が別の排除を生む恐れもある。
代わりの視点:著者は、社会は「既に多様な能力と状況をもつ人」で成り立っており、その中で何をどう支援すべきかを柔軟に考える必要があると論じる。
第8章 とは何か?と問うを問う
障害を「何か」と定義づけること自体の是非を問う章。障害学の議論では、「障害とは何か」をめぐってさまざまな理論が提示されるが、著者は「定義づけ」にこだわることの限界を示唆します。
星加良司『障害とは何か』:障害学の枠組みを整理しながら、その可能性と問題点を分析。
社会モデルvs.身体モデル:原因論や責任論に陥るよりも、現在ある生きづらさをどう解消するかに焦点を当てる必要がある。
第9章 普通に社会科学をする
障害をめぐる問題を、特別なテーマとしてではなく「普通の社会科学の課題」として扱うことを提唱。障害をめぐる研究は、社会学、経済学、政治学などの多分野で当たり前のように考察されるべきだという主張です。
不利益の集中:障害をもつ人に不利益が集まりやすい社会構造を、社会科学的なデータを通して明らかにし、制度設計を検討する。
定義論からの転換:障害の定義をめぐる抽象的な議論よりも、実際の生活上の困難の解消を目指す方が社会学的に有意義だと説く。
第10章 ないにこしたことはない、か・1
「できないこと」は本当に「ないに越したことはない」ものなのかを考察します。痛みや死以外にも、障害によって「できないこと」があるが、そこに価値や意義を見出す可能性もあると説きます。
本人にとってのプラス面:障害があることで得られる役割や人間関係があり、「必ずしもゼロかマイナスではない」という視点。
周囲や社会にとって:介護や支援は負担になるかもしれないが、一方で「助け合い」のネットワークを生み出す側面もある。
第11章 なおすことについて
「なおす(治す)」こと自体の是非をより踏み込んで論じます。医療・リハビリテーションと本人の意向、社会のコストとの関係を考慮する必要性を強調。
リハビリの意味:本人が望むリハビリとは何か。社会や専門家が押し付けるリハビリとのギャップが問題になる。
価値の測定:治療や手術によって「失われる」ものと「得られる」ものを比較し、本人が納得できる選択を支える仕組みが必要。
第12章 存在の肯定、の手前で
作業療法やリハビリテーションが「存在を肯定する」行為になりうるのかを問う。痛みや死、能力の限界といった厳しい現実を前に、どう「生きることの意義」を見出すのかを考える。
できることを増やすだけが目的ではない:患者や障害者が「ここにいるだけで良い」という価値を認める姿勢が必要。
社会が見る価値と本人が感じる価値:両者をすり合わせる中で、本当に必要なケアや支援が見えてくる。
第13章 障害者支援・指導・教育の倫理
障害者支援や教育の現場での倫理を取り上げ、自閉症スペクトラムなどを例にしながら、専門家と当事者との関係を考察します。
自閉症連続体:一律に「できる/できない」を決めつけず、多様な特性に応じた支援や教育が求められる。
現場での実践:マニュアルに沿うだけではなく、個々人に合った柔軟な対応をとる必要がある。
第14章 リハビリテーション専門家批判を継ぐ
リハビリテーションの専門家や医療従事者が障害者をどう位置づけるか、歴史的な経緯を踏まえて批判的に検討。かつて賞賛されてきたリハビリ専門家の言説にも、当事者から見ると問題があったことを指摘します。
専門家中心のリハビリ:専門家が「できること」を増やすことを重視しすぎると、本人の意思や生活全体を軽視しかねない。
批判を継いで前進する:リハビリテーションは必要だが、当事者の主体性を尊重する形に再構築していくべきだと結論づける。
3. 鍼灸治療への生かし方
立岩の議論を鍼灸治療の実践に当てはめるとき、身体だけでなく社会環境や当事者の価値観を含めた包括的なアプローチが重要です。ここでは、10の観点を示します。
① 治すことだけが目的ではない
鍼灸師は「病や障害を完全に取り除く」のではなく、症状緩和や生活の質向上を目指すことができる。たとえば、疼痛の軽減や可動域の改善など、小さな変化でも本人にとって大きな意味を持つ。
② 五つの要素を見極める
患者の抱える問題が「苦痛」「死」「できないこと」「異なること」「加害性」のうち、どれに当てはまるのかを意識する。そうすることで、鍼灸治療の目標設定がはっきりし、患者への説明もしやすくなる。
③ 社会モデルの視点を取り入れる
痛みや不調を、単なる個人の身体的課題と見なすのではなく、職場環境や家庭環境など社会的要因も含めて検討する。例えば、再発しないように周囲の協力体制を整えることも鍼灸師のアドバイス領域になりうる。
④ 患者の意向とペースを尊重する
リハビリや治療を押し付けるのではなく、患者が「どの程度まで改善したいのか」を丁寧にヒアリングする。本人が望まない治療は、たとえ医学的には効果があってもストレスや抵抗を生む。
⑤ 痛みや苦痛の意味を共有する
痛みは身体的なシグナルとしてだけでなく、心理的・社会的文脈と結びついている。患者が抱える苦痛の背景には、家庭や職場のストレス、人間関係の問題が潜んでいることも多い。
⑥ 在宅・地域支援との連携
鍼灸師がクリニックや自宅訪問で施術する際、介護ヘルパーや訪問看護師などと情報交換を行うことで、患者の生活全体を把握しやすくなる。社会資源を上手に活用しながら、症状緩和だけでなく日常生活のサポートにもつなげる。
⑦ 長期的なフォローアップ
立岩の議論にあるように、「治す」よりも「支え続ける」という考え方が重要。鍼灸治療でも、定期的なメンテナンスを行いながら、患者の状態や環境変化に対応していく。
⑧ 多職種との協同
医師やリハビリ専門職だけでなく、ソーシャルワーカーや心理カウンセラー、福祉士などとも協力することで、患者の課題を多角的に捉えることができる。鍼灸は身体面でのケアを担いつつ、必要に応じて他分野の支援を紹介する。
⑨ 痛みや障害を「否定」しない
「痛みは早く取るべき」「障害は治すべき」といった一元的な価値観を押し付けず、「不如意な身体」を肯定する視点を持つ。たとえ痛みや障害が残っても、それと共に生きるための施術を考えることが大切。
⑩ 患者の語りを重視する
鍼灸師は患者の身体に触れる機会が多いが、同時に患者本人の語り(不安や希望、日常で困っていること)に耳を傾けることで、より適切な施術方法が見えてくる。立岩の言う「本人の声」を大切にする姿勢が求められる。
4,まとめ
立岩真也の『不如意の身体』は、病や障害を考えるうえで、「身体だけでなく社会や環境も含めて見る」ことの重要性を訴えています。鍼灸治療においても、以下の点を意識することで、患者一人ひとりに応じた包括的なアプローチを実現できます。
完全に治すことが困難でも、痛みの軽減や生活の質向上に大きく寄与できる。
病や障害を個人だけでなく、社会的要因や環境と結びつけて考える。
患者の主体性を尊重し、必要に応じて多職種と連携しながら長期的な支援を行う。
鍼灸は単なる対症療法やリラクゼーションではなく、患者の「生き方」を支える役割を果たせる可能性を持っています。『不如意の身体』で示される多角的な視点を取り入れることで、鍼灸師としての治療やケアがより深みを増し、患者の人生をより良いものへと導く手助けとなるでしょう。