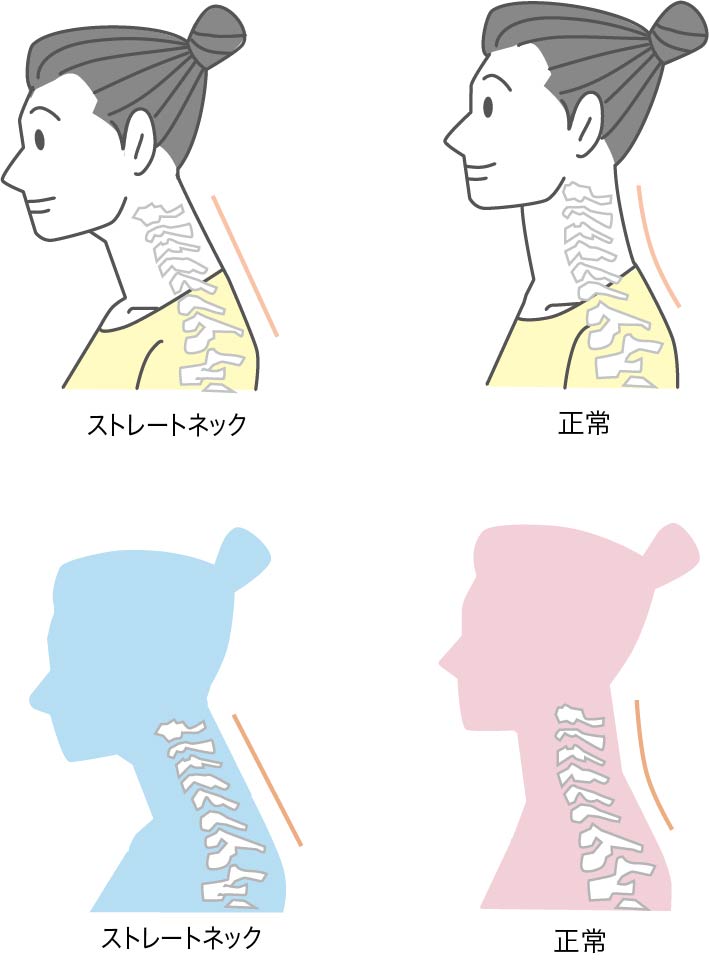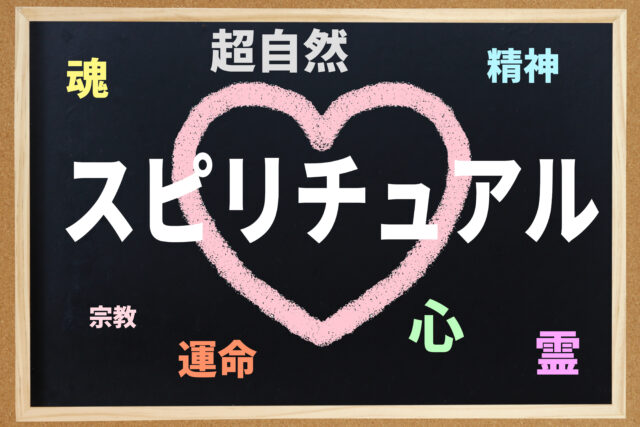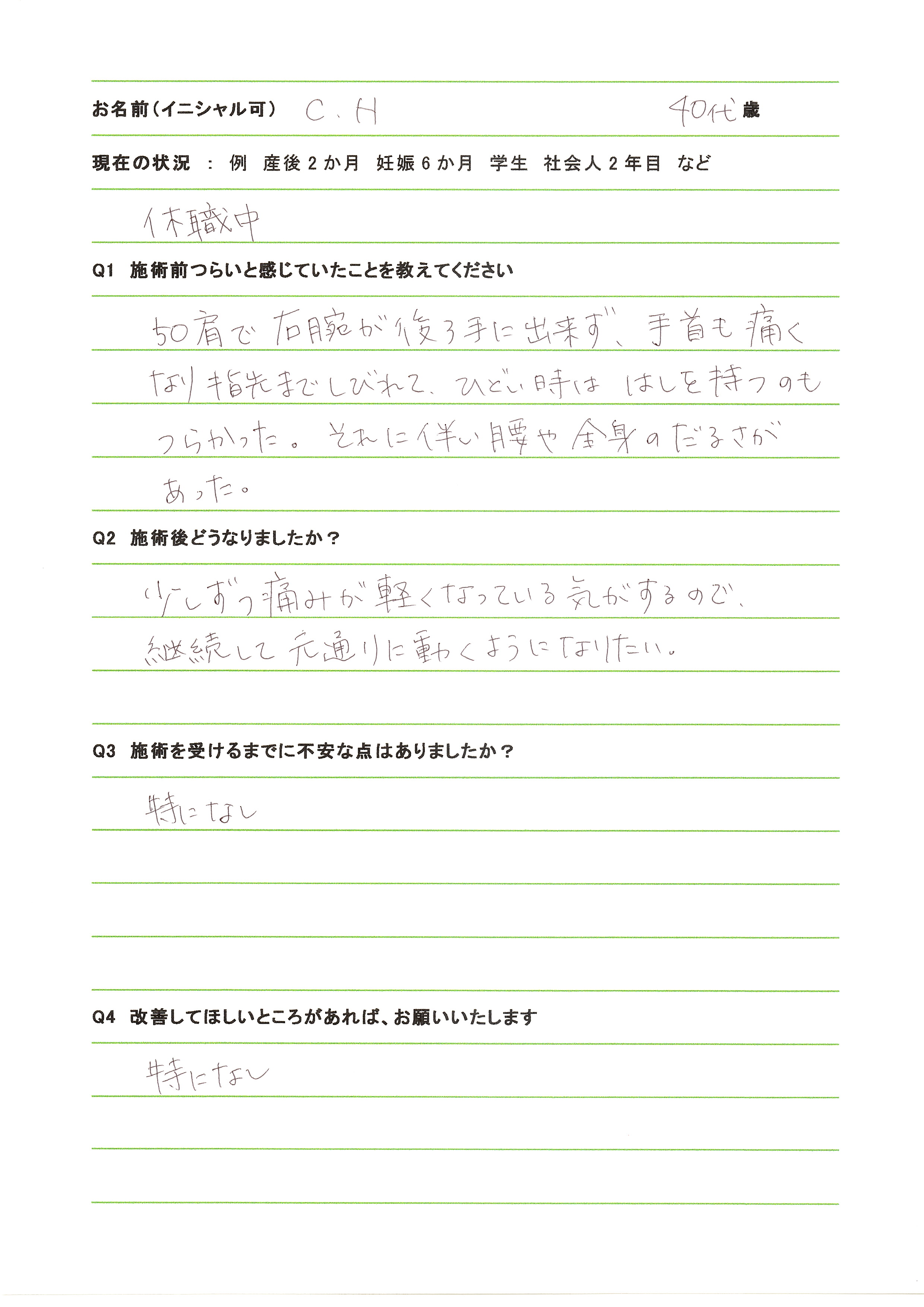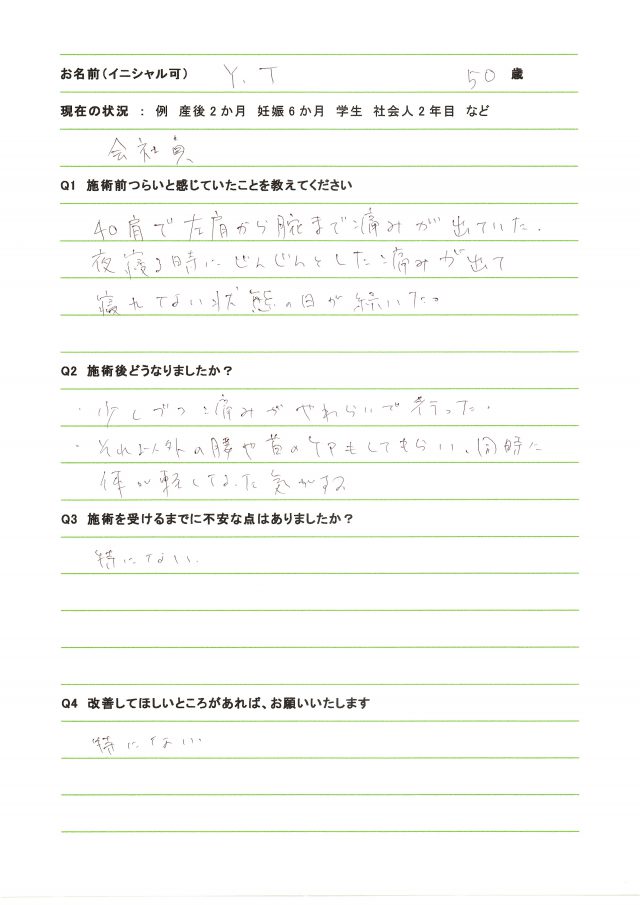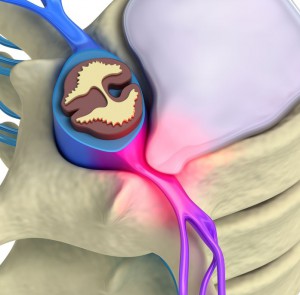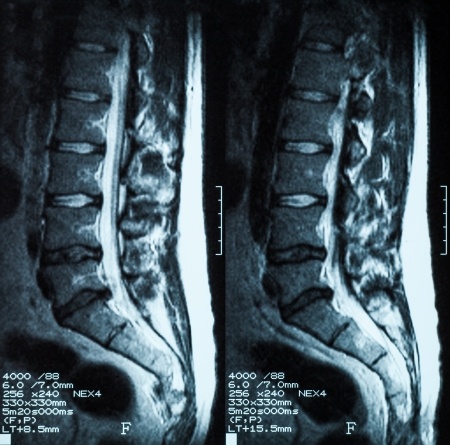鍼灸治療が発達障害そのものを緩和するというエビデンスはありませんがストレスを和らげ、緊張を緩和する可能性があるため症状改善のお役に立てます。以下に情報をまとめておきますが発達障害をお持ち、またはその疑いがあり体調不良でお困りの方は一度お気軽に相談ください。専門的に診断してくれる医療機関を紹介したりしながら併用して鍼灸施術を受けることもできます。*似たような事例では、子供の起立性調整障害疑いを鍼灸施術を行いながら専門病院におつなぎした事例があります。
発達障害の定義とは?
発達障害者支援法において、「発達障害」は「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定義されています。(厚生労働省)
脳の機能的な問題が関係して生じる疾患であり、日常生活、社会生活、学業、職業上における機能障害が発達期にみられる状態をいいます。 最新のDSM-5(「精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版」)では、神経発達障害/神経発達症とも表記されます。(eヘルスネット・厚生労働省)
DSM-5に基づいて診断基準や分類がなされます。
発達障害と「発達に課題がある」という状態の違いをとは?
「発達障害でなく発達に課題がある」という表現には、いくつかのニュアンスが含まれています。以下、それぞれの状態に関連する特徴や違いを説明します。
(1)発達障害
・明確な症状と診断:発達障害は、特定の症状や特徴が明確に現れ、これに基づいて診断が行われます。
・DSM-5(精神障害の診断および統計マニュアル)などの基準に適合:発達障害の診断は、一般的に国際的に受け入れられた診断基準に基づいています。
・症状が生涯にわたり持続:発達障害は、生涯にわたって続く可能性が高い慢性の状態であることが多いです。
(2)発達に課題がある
・特定の状況や期間に関連:発達に課題がある場合、それが特定の状況や期間に関連している可能性があります。例えば、一時的な学習の課題やストレスによる影響が考えられます。
・明確な症状がない場合も:発達に課題がある場合、明確な症状がないか、症状が一時的であることがあります。
・他の要因による可能性:発達に課題がある場合、環境の変化、一時的なストレス、他の健康状態などが原因となっている可能性があります。
簡潔に言えば、発達障害は比較的に持続的で明確な症状を伴う一般的な診断であるのに対して、発達に課題がある場合は一時的で特定の状況や期間に関連している可能性があります。ただし、具体的な状態や症状は個人によって異なり、専門家の評価が必要です。
発達障害の分類は?
eヘルスネット・厚生労働省の解説ページを参考にDSM-5の分類を紹介します。
発達障害は、いくつかの主要なカテゴリーに分類されます。以下に、主な発達障害の分類を示します。なお、これらのカテゴリーはあくまで広い範囲であり、個々の人が抱える症状や特徴は非常に多岐にわたります。
・注意欠陥多動性障害 (ADHD):短縮してADHDとも呼ばれます。注意の欠如、過動、衝動性が特徴で、学業や社会的な機能に影響を与えることがあります。
・自閉スペクトラム障害 (ASD):自閉症スペクトラム障害は、コミュニケーションの障害や社会的な相互作用の難しさ、独特な興味や行動の繰り返しといった特徴を持つ総称です。高機能自閉症から、深刻な発達障害まで幅広い症状があります。
・学習障害:読み書きや計算などの学習に関連する領域で困難を経験する総称です。ディスレクシア(読字障害)、ディスカルキュリア(計算障害)などが含まれます。
・知的障害:一般的な知的機能の発達が遅れるか、制限される状態を指します。IQが一定の基準以下であることが一般的な特徴です。
・発話・言語障害:発音、語彙、文法などの言語に関する困難が含まれます。言語発達障害や発声障害などが該当します。
これらの障害は、個々の人の特性や症状によって様々な程度で現れ、また同時に複数の発達障害を抱えることもあります。診断やサポートのためには、適切な専門家や医療プロフェッショナルに相談することが重要です。
大人になるまで発達障害が放置されてしまうケースがあるのはなぜ?
発達障害は子供だけというイメージがあるかもしれませんが大人もあり得ますし、また大人になるまで放置されるケースがあります。その理由は複雑であり、さまざまな要因が関与しています。以下はその主な理由です。
・軽度であるため気付かれにくい:発達障害が軽度である場合、症状が他の一般的な行動の範囲内に収まることがあります。そのため、問題があると気付かれにくいことがあります。
・社会的な期待の変化:子供時代から大人にかけて、発達障害の特徴は変化することがあります。また、社会の期待も変わり、大人になると共に異なる対応が求められることがあるため、発達障害が見過ごされることがあります。
・マスキングやコンピェンセーション: 発達障害を持つ人は、自身の困難に対処するために異なる戦略を学びます。これにより、一時的には症状が緩和されたり、他者に隠されることがあります。
・診断の難しさ: 発達障害の診断は複雑であり、専門的な知識と時間を要します。一般的な診断は子供時代に行われやすいため、大人になると診断が難しくなることがあります。
・周囲の理解の不足:発達障害についての理解が不足している場合、症状が異常であることに気付かないか、適切なサポートが得られないことがあります。
・自覚の不足:発達障害を持つ人自身が、自分の特徴が他と異なることに気付かない場合があります。また、気付いてもそれを受け入れるのが難しい場合もあります。
これらの要因が複合的に絡み合って、発達障害が大人になるまで放置されることがあります。早期の診断と適切なサポートが重要であり、理解ある環境でのサポートが提供されることで、大人になってからの生活の質が向上することが期待されます。
発達障害の人がストレスに弱いのはなぜですか?またできるセルフケアや対策はありますか?
発達障害を持つ人がストレスに弱いと感じる理由は、いくつかの特性や課題が絡み合っている可能性があります。一般的な特徴として以下の点が挙げられます。
・感覚過敏:発達障害を持つ人々は、外部の刺激(音、光、触覚など)に対して過敏であることがあります。過度な刺激がストレスを引き起こす可能性が高まります。
・社会的な適応困難:コミュニケーションや社会的な相互作用において適応が難しいことがあり、これが社会的なストレスや孤立感を引き起こすことがあります。
・予測困難性:変化への適応が難しいことがあり、予測可能でない出来事がストレスとなることがあります。
・コミュニケーションの困難:意思疎通が難しい場合、自分の感情やニーズを適切に伝えることが難しく、これがストレスの原因となります。
これらの理由から、発達障害を持つ人がストレスに敏感であると感じることがあります。しかし、適切なセルフケアや対策を取ることで、ストレスへの対処が改善される可能性があります。以下はその一例です。
・ストレス管理技術の学習: リラクセーション法、深呼吸、瞑想などのストレス管理技術を学ぶことで、ストレスに対処する能力が向上します。
・コミュニケーションスキルの向上:コミュニケーションスキルのトレーニングや、感情やニーズを適切に伝える方法を学ぶことが、ストレスの軽減に寄与します。
・予測可能な環境の構築:予測可能な環境を作り出すことで、変化に対処しやすくなり、ストレスを軽減できます。
・適切なサポートの確保:必要なサポートや理解ある環境を確保することが重要です。家族や友人、教育機関、職場などからのサポートが役立ちます。
個々のケースによって適したアプローチが異なりますので、専門家と相談し、個別のサポートプランを立てることが重要です。
鍼灸治療は発達障害の症状を緩和しますか?
以下は、鍼灸治療がストレスに対してどのように影響を与えるかに関する一般的なポイントです。
・リラックス効果:鍼灸治療は、鍼や灸を用いて特定の経絡やツボに刺激を与えることで、筋肉の緊張を緩和し、リラックス効果をもたらすことがあります。これにより、身体的なストレスや緊張が和らぐ可能性があります。
・自律神経の調整:鍼灸治療は、自律神経系を調整する助けとなることが報告されています。具体的には、交感神経(ストレス応答を活発化する)と副交感神経(リラックスを促進する)のバランスを整える働きが期待されます。
・ホルモンの調整:鍼灸治療がストレスホルモンや神経伝達物質のバランスを調整する可能性があります。これにより、ストレス応答が緩和されることが期待されます。
・睡眠の改善:ストレスが原因で睡眠障害が生じることがありますが、鍼灸治療が睡眠の質を向上させ、ストレスの軽減に寄与するとされることがあります。



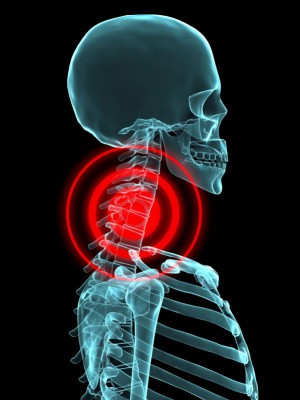
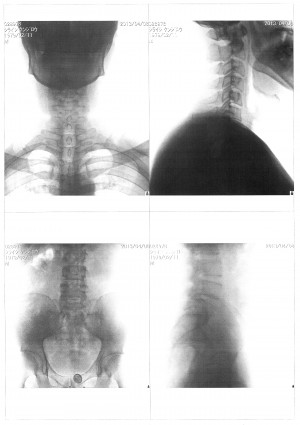




_page-0001.jpg)