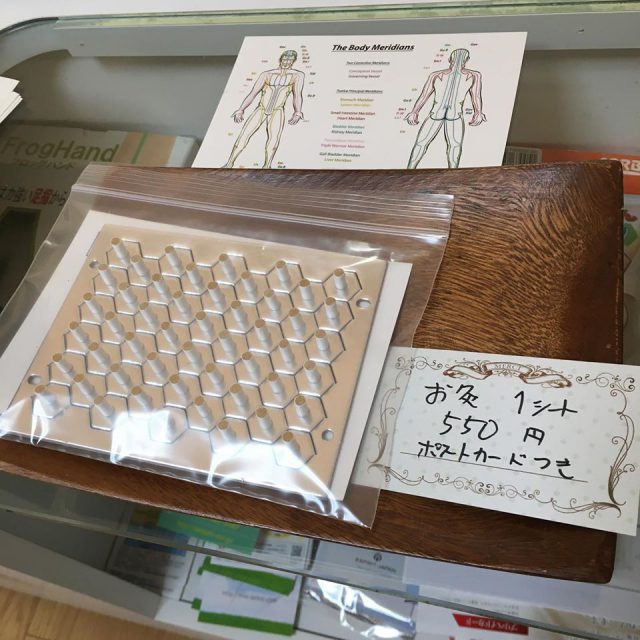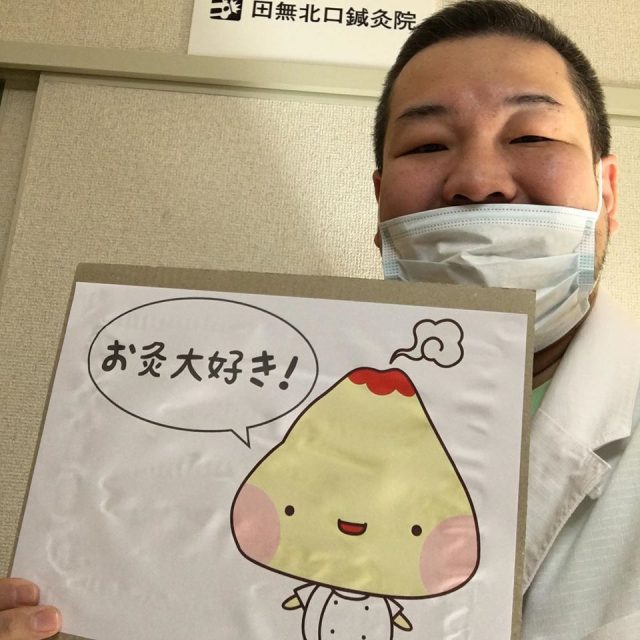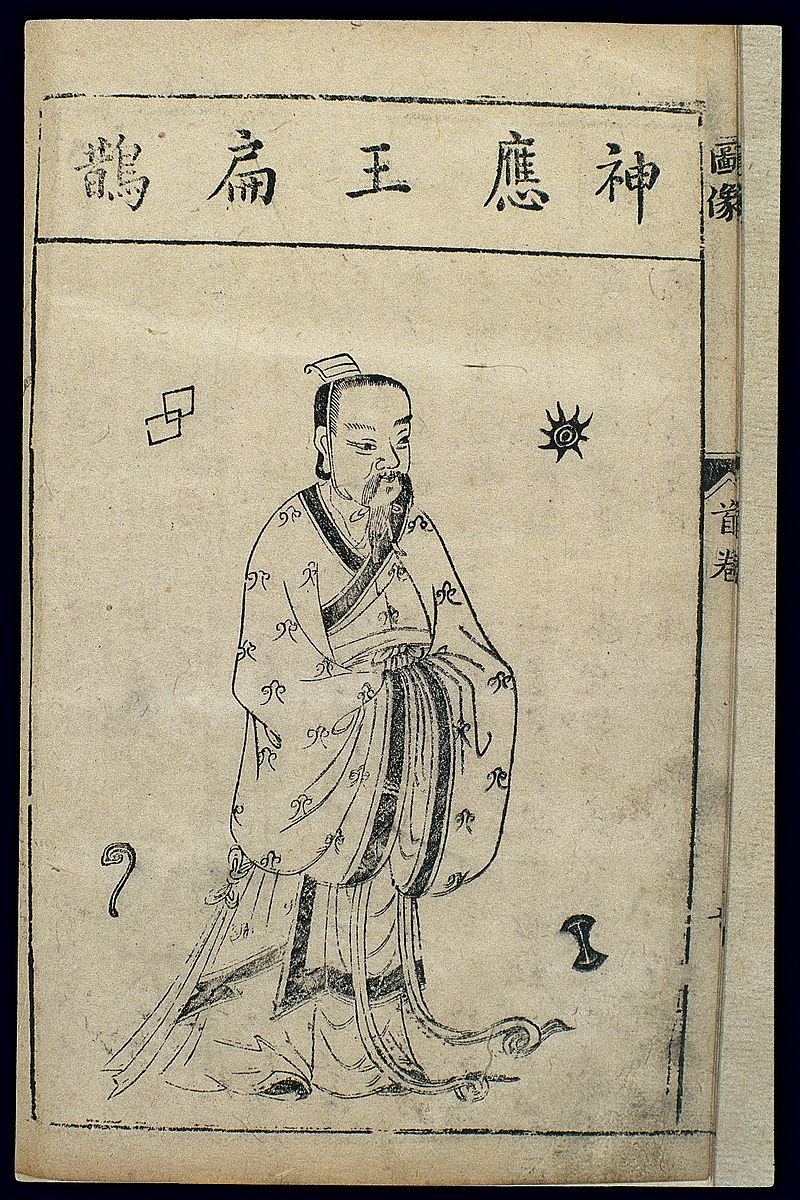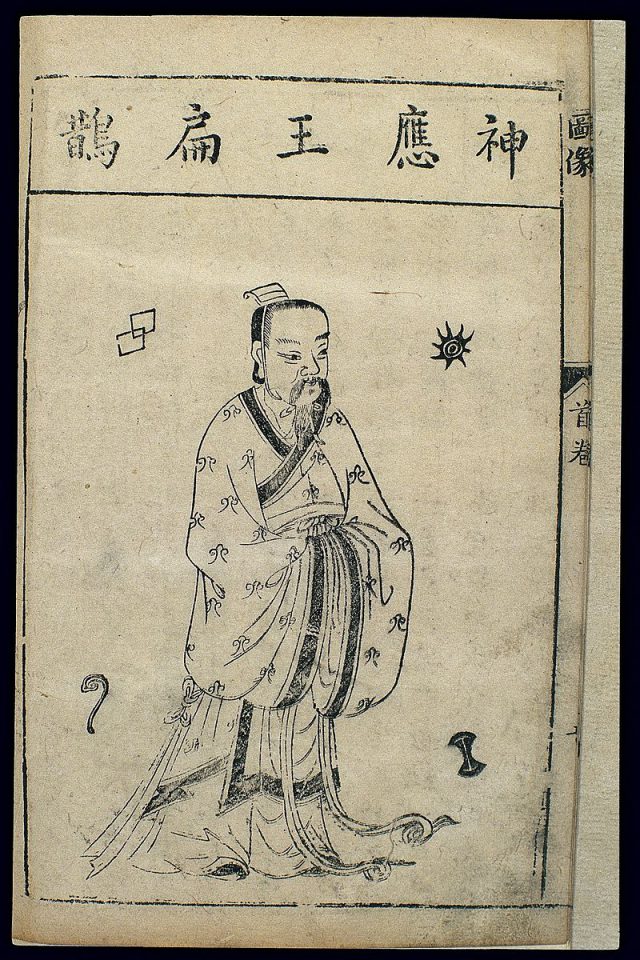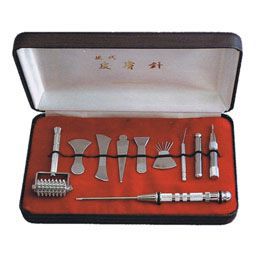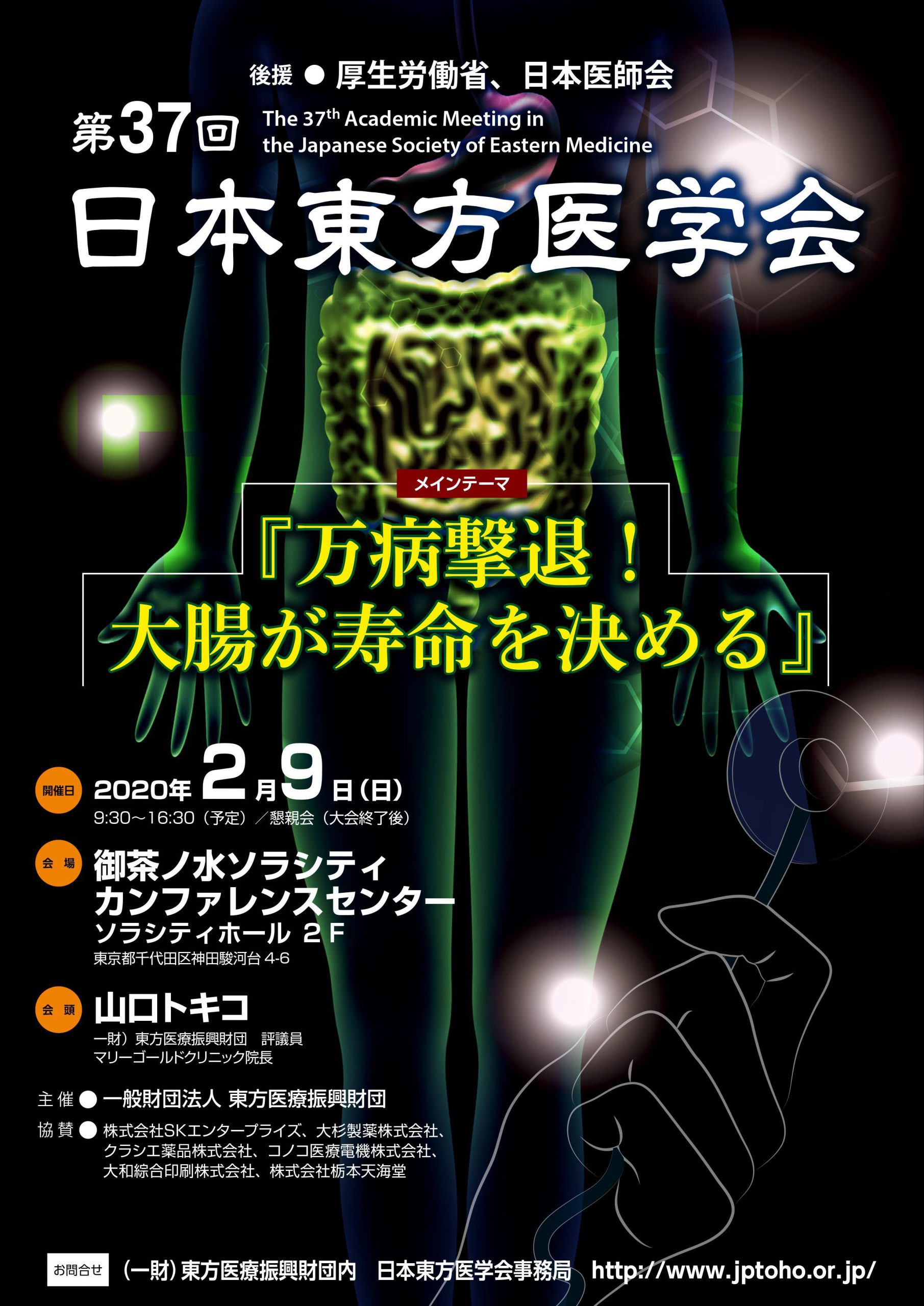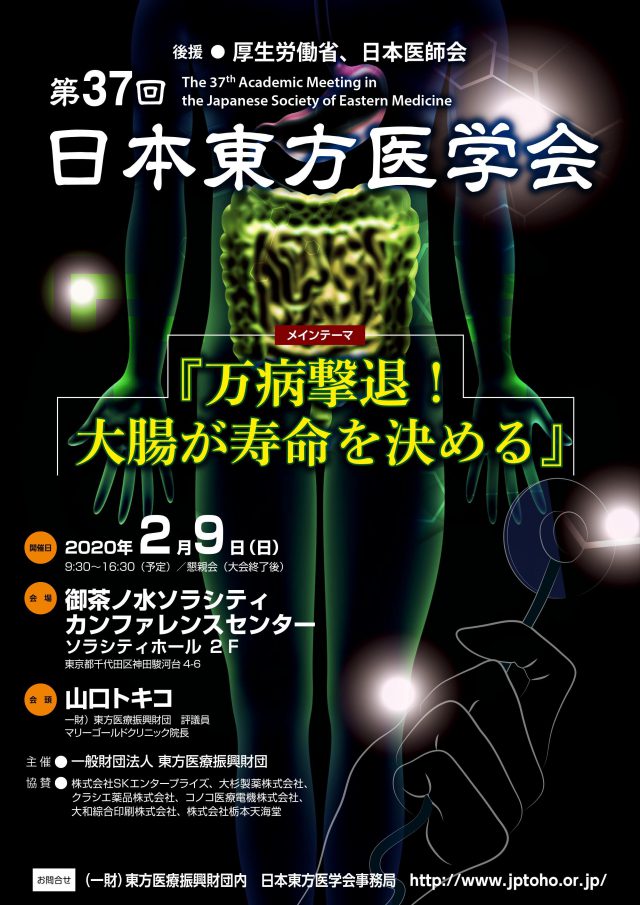弊所は病院と連携しているということを一つのアピールにしてます。今回は連携しながら施術した症例報告をします。がんの手術後腰痛になった患者さんを取り上げました。
病院と連携することでそのような持病を持つ方も安心して見れるようになるのは大きな強みでしょう。動画でも説明していますが鍼灸は補完治療がメインです。極端な話はしませんが安心して施術を受けてくだされば幸いです。(以下・症例)
>>>>>>>>
本症例は胃がんの術後4か月後より腰部・背部の痛み、およびめまい不調が発生し鍼灸治療と医師による漢方処方により症状が改善した例である。週に1,2回の鍼灸施術11回程度で症状が改善した。鍼灸院だけでなく医師の診察や処方による治療の相乗効果が示唆された。
お名前:
桜井 花子さま(仮名)45歳女性 主婦
初診:
平成30年3月5日
主訴:
左腰痛・背部痛、めまい、自律神経症状
既往歴:
胃がん
現病歴:
平成29年12月 某F総合病院で胃がん手術。1/3摘出。術後からしばらくして主訴である腰痛・背部痛、自律神経症状が発生。
平成30年2月頃、近所のF総合病院にて診察。シップ薬処方のみで満足が得られなかったため弊所を受診した。鍼灸治療に期待している。発生時期・発生状況は不明だが術後しばらくたってから主訴が気になり始めたとのこと。
家族歴:
特筆することは特になし
所見・方針:
全身の筋緊張あり。頸部・左背部の緊張がとくに強い。腰痛のためSLRテスト実施。陰性。平成30年2月にF総合病院にて脳CT検査。異常なし。
筋緊張や心因性のものが原因であると推測。
術後からがんに効果があるとされる健康食品も服用。知人に勧められた。
既往歴や心因性の原因から鍼灸だけでなく漢方も併用したほうがいいと判断し漢方内科への受診も勧める。受諾してもらう。漢方内科クリニック紹介。
施術:
乳がんの告知後から体調が悪くなったようなので精神的な不安を取りのぞけるよう現在の通院や投薬状況など伺う。ある程度の治療計画を立て改善までの目安も伝えた。最初は集中的に施術を行い少しずつ間を開けていく。うつ伏せの状態で施術は胸が気になるのでバスタオルやマットで調整。不安感が出ないようにしながら施術。背部兪穴に鍼・温灸。特に肝兪・膈兪が硬い。風池・亜門・完骨など自律神経症状の改善目的で頚周辺の経穴にも刺鍼。
経過:
1回目 3/7時間をかけて問診を行う。自律神経症状や検査についても細かく記入してもらい、よくお話を伺った。施術計画についても説明。同意を得る。漢方内科も紹介できる旨伝える。
*必ず行かなければいけないわけではない。
2.3回目 3/11.3/14
引き続き緊張を取る目的の施術。施術レポートをお渡しし現状について理解を深めてもらう。
4・5回目 3/16.3/18
施術アンケート実施。現状感じている疑問や不安を吐き出してもらい施術にフィードバックさせる。やはり病気のことが気になるようでマインドフルネス(瞑想)のお話などもお伝えする。選択肢を多く持つことで不安感を減らしてもらう。また漢方内科への通院も希望したために紹介状渡す。
6回目 3/25
漢方内科受診。投薬開始。お手紙をもとに施術方針について再度説明。何かあれば医師にも相談するよう伝える。
7.8.9回目 4/1、4/9、/17
緊張緩和。疼痛改善傾向。
10回目 4/23
改善傾向のため今後は自宅でのセルフケア(お灸など)継続しつつ少し間を開けて施術しメンテナンスするよう説明。漢方内科・鍼灸院ともに月に1.2回程度は通院するよう指導。
生活指導:
自宅でセルフケアでできるお灸やマインドフルネス瞑想のことなどもお伝えしなるべく多くの選択肢を持ってもらうことで精神的なゆとりを持ってもらった。
考察:
がんの補完代替医療として健康食品や代替療法に費やすお金はなんと月平均57000円、年間で684000円という情報がある。*参考 国立がん研究センター「統合医療は信用できるか?」より 鍼灸師は鍼灸というタッチセラピーを通し患者の不安感を取り除いたうえで正しい情報を患者に与え漢方を処方できる医師とも協力しがん患者の施術・鍼灸治療に当たればこの費用を今より安く抑えなおかつ安全に治療効果も高めることができ患者満足度が高い治療を提供できるのではないか?と考えている。引き続き医師と連携しながらのがん患者の鍼灸治療にあたりたい。